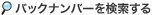バックナンバー
2020年9月7日 2850号

武器は走りながら拾え
『ニューヨークBIZ』発行人兼CEO
高橋克明さん
圧倒的準備不足の中、決断したニューヨーク行き
…僕は、誰もが認める世界のトップリーダーとお話しする機会を得ました。これまで、ハリウッドスターではトム・クルーズ、レオナルド・ディカプリオ、日本人ではX JAPANのYOSHIKI、渡辺謙、アスリートではデイヴィッド・ベッカムや松井秀喜など、1000人以上のそうそうたる人々にインタビューしてきました。「有名な人にインタビューできてうらやましい」と、よく言われます。でも…【続きはこちらから】
社説
「畏れを抱く。人間の分際なのだから」
魂の編集長 水谷謹人
…ふと、こんな話を思い出した。一人の男が大木を伐っていた。朝からずっと必死にのこぎりを引いていたのだ。通りかかった老人が不思議に思って声を掛けた。「いくらのこぎりを引いても伐れていないのは刃が丸くなっているからです。刃を研いだほうがいいですよ」しかし、男は…【続きはこちらから】
2020年8月24日 2849号

人に子どもに光あれ
子ども家庭教育フォーラム代表/教育・心理カウンセラー
富田富士也さん
「還る家」はありますか?!
…私のカウンセリング経験から言うと、「いい子」はどこかで「報われなさ」を持っていたりします。成績がよくておとなしくて、弱音や愚痴を言わない「いい子」ほど、見た目は何の問題もないように見えます。でも、そういう子にも憂いがあったりするのです。そして思いがけない納得しがたい出来事をきっかけに…【続きはこちらから】
社説
「正義の先にある温かいもの」
中部支局長 山本孝弘
…インドに「ダウリー」と呼ばれる風習がある。娘が結婚する際に父親が年収の何十倍もの持参金や家具を婿側に贈る習わしである。『シティ・オブ・ジョイ』という映画には、ダウリーのために多額のお金が必要となった貧しいインド人の男が登場する。彼はあらゆる手を使って観光客からお金をぼったくっていく。私も…【続きはこちらから】
2020年8月17日 2848号

発見! わくわくエンジン
認定NPO法人キーパーソン21代表理事
朝山あつこさん
「わくわく」は可能性の宝箱!
…ある中学校で野球部に所属していた3人の生徒がいました。私たちがその中学校で実施したプログラムの中で、彼らは3人とも自分がわくわくするものを「野球」と答えました。大人はこういう子に「じゃあ、将来は野球選手になればいいね」などと、簡単に言ってしまいます。すると…【続きはこちらから】
社説
「年を取っても勝手に創れる若々しさ」
魂の編集長 水谷謹人
随分前の小欄に放送作家・永六輔さんのことを書いたことがある。永さんは子ども時代にいじめられていた。自分をいじめた連中に会いたくないので、成人してから同窓会には一度も出席したことがなかった。還暦の年、同世代の人が健康を害したり、病気で亡くなっていくのを見て、昔の友人のことが気になり、同窓会に初めて顔を出した。気になったのは…【続きはこちらから】
2020年8月10日 2846号

伝え方のレシピ
コピーライター/作詞家/上智大学非常勤講師
佐々木圭一さん
プロが唸った、上手な伝え方 ~ファストフード店員から言われた一言~
…テレビを観たり誰かの話を聞いたりして、「この言葉沁みるな」と思うことってありますよね。そういうものを見つけたら、僕は必ずノートにメモを取っていたんです。ある時そのノートを見ていたら、「これらの言葉には共通点がある」と気づきました。これは、…【続きはこちらから】
社説
「赤紙を受け取った乙女たちがいた」
魂の編集長 水谷謹人
兵庫県小野市の開業医・篠原慶希(しのはら・よしき)さんからバーコードのない一冊の本が届いた。自費出版されたものだろう。同じ町に住む御年(おんとし)95歳の治居冨美(はるい・ふみ)さんの本である。恥ずかしながらこの本を読むまで、戦時中、召集令状(赤紙)を受け取った女性たちがいたことを知らなかった。冨美さんは言う。「“明日があるから”なんて思えない時代でした」と。そして、…【続きはこちらから】
2020年8月3日 2845号

学校を作り直す
哲学者/教育学者/熊本大学教育学部准教授
苫野 一徳さん
哲学が読み解く「学校教育とは何か」
…今回は「学校を作り直す」ということで、まず、次のことを皆さんと共有したいと思います。「公教育(学校教育)は市民社会の最大の土台であり、人類数万年の歴史における革命的な発明である」と。公教育によって、全ての子どもが「自由」に生きるための力を育みます。それと同時に、全ての子どもが対等に「自由」な人間であるという感度(感受性)も育む―これが公教育の本質です。この公教育の本質は…【続きはこちらから】
社説
「劇場に足を運ぶことを忘れないで」
魂の編集長 水谷謹人
劇場に足を運ぶことを忘れないで
芥川賞作家で、お笑い芸人の又吉直樹さんの小説『劇場』が映画化されたのだが、なんと7月17日の劇場公開と同時に、アマゾンプライム・ビデオでネット配信されている。映画は、出来る限り映画館に足を運んで観るのが制作者・出演者に対する礼儀だが、昨今の状況を鑑みた配給会社の吉本興業がステイホームでも鑑賞可能にしたのである。この物語は、…【続きはこちらから】