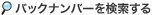バックナンバー
2019年8月12日 2800号

人を動かすPR その1
PRプロデューサー/株式会社TMオフィス代表取締役
殿村美樹さん
漢字検定はどうやって定着したか?
私は約30年間、地方のPRをメインに仕事をしてきました。通常、PR(パブリック・リレーションズ)とは、特定の商品(モノやサービス)を広く知ってもらうために、メディアに取り上げてもらうための企画を練ったり、イベントを行ったりすることを言います。しかし、…【続きはこちらから】
社説
「死と共に消え去らないように」
魂の編集長 水谷謹人
長年、「語り部」として原爆被爆者の声を発信してきた米澤鐵志さん(85)の話はずっしり心に響く。紙面に載せづらい生々しい表現を含んだ原稿は、8月19日号・最終回の際に本紙HPにアップする。元特攻兵の栗永照彦さん(92)の話を掲載したのは2016年8月15日号だった。戦後、戦争中の体験を語ることがなかった栗永さんは…【続きはこちらから】
2019年8月5日 2799号

あの日、あの夏 その1
原爆被爆者/語り部
米澤鐡志さん
空が光った日~11歳の少年が見たヒロシマ~
私は今年の夏に85歳になります。小学校5年生の時に、広島の中野の近くで原爆を受けました。その当時のことをお話しさせていただきます。私の父親は軍医としてフィリピンに召集されていました。ですから母と、私を筆頭に5人の子どもたちとで暮らしていました。さらに戦争中でしたので…【続きはこちらから】
社説
「出会いはいつも人知を超えて…」
魂の編集長 水谷謹人
20年ほど前、女子刑務所を長年慰問してきた放送作家・永六輔さん(故人)の話を小欄に書いたことがある。当時、全国の刑務所に服役している受刑者は約4万3000人で、そのうち女性は2200人ほどだった。…女性の犯罪にはちょっとした特徴がある。受刑者の約7割が…【続きはこちらから】
2019年7月22日 2798号

とびだせ花開け その1
アットマーク国際高校・明蓬館高校理事長/日本ホームスクール支援協会理事長
日野公三さん
「特別な注文」に応じた支援の場がある
今、海外で障がいのある方をどう表現するかご存じでしょうか。これはアメリカの場合ですが、現在は一般的に「ピープル・ウィズ・スペシャル・ニーズ(people with special needs)」、「特別な注文主」という名称になっています。一頃は「ハンディキャッパー」なんていう言葉がありましたが、これは今絶対に使ってはいけない言葉になっています。なぜか?…【続きはこちらから】
社説
「歳月が隠してきた葉書の中の愛」
中部特派員 山本孝弘
朝日放送テレビの『探偵! ナイトスクープ』という番組がある。視聴者からのあらゆる相談を解決していくバラエティ番組だ。若干ふざけたような相談から真面目な相談まで幅広く取り上げる。以前、こんな相談が寄せられた。「私が母の胎内にいた時に父はレイテ島で戦死しました。しかし父は母のお腹に私がいることを知っていたのか分かりません…【続きはこちらから】
2019年7月15日 2797号

ロボットとともに生きる その1
東京理科大学工学部教授/株式会社イノフィス創業者・取締役
小林 宏さん
「一生寝たきり」の人がロボットで歩ける未来
「ロボット」という機械システムは、20世紀に著しく発達し、人間を多くの肉体的重労働から解放しました。では今後、人は機械システムに何を求めるべきでしょうか。肉体的負担の解放は引き続き必要ですが、それに加え…【続きはこちらから】
社説
「山あり谷ありの星だから素晴らしい」
魂の編集長 水谷謹人
そう言えば、美術館や博物館、動物園などの社会教育施設には何度も訪れたが、天文台には行ったことがなかった。これを機に行ってみようと思った。雨の日の動物園が楽しくないように、「夜空の動物園」に行くのも晴れた夜がいい。星のパンダや象はいないが、「白鳥(ハクチョウ)」や「子熊(コグマ)」「山羊(ヤギ)」たちが観られる。ただ、…【続きはこちらから】
2019年7月8日 2796号

笑顔で迎える人生の最終章 その1
緩和ケア萬田診療所院長
萬田緑平さん
「かっこつけ」の彼女の完璧な「終活」
乳がんで手術と抗がん剤治療が必要と診断された女性がいました。バリバリ仕事ができる女性で、バイクが趣味でした。…彼女は考えました。「治療に専念すると、仕事も辞めてバイク仲間とも恋人とも離れることになる。そしたら生きていても何も残らない」。そこで彼女は…【続きはこちらから】
社説
「苦笑いするか仰天するか怒り出すか」
魂の編集長 水谷謹人
アンデルセンの童話に『マッチ売りの少女』という作品がある。…大人になってこの童話を読み直した中小企業診断士の平野喜久さんは、職業柄「なぜマッチは売れなかったんだろう」と素朴な疑問を持った。そして勝手にその続きを、童話調のままビジネス本にした。それが…【続きはこちらから】