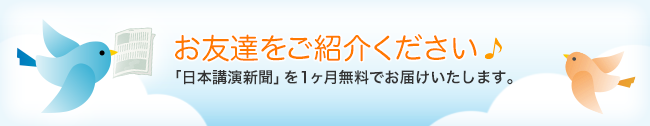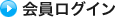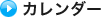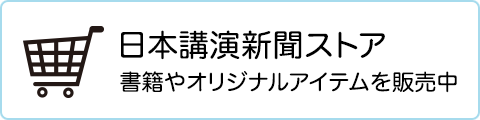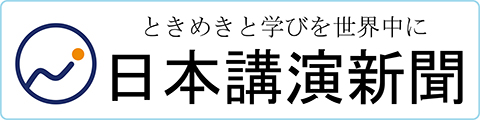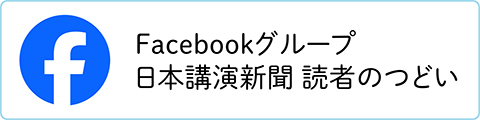くるみの談話室 2559号(2014/06/23)
知らなかった郷土の偉人
本紙代表 松田くるみ
先月書店の店頭に並んだ拙著『なぜ、宮崎の小さな新聞が世界中で読まれているのか』がお陰様で好評です。私はこの本が出た時、まず本紙の創業者、外山慶秋(とやま・けいしゅう)氏のお墓参りに行き、感謝の気持ちを伝えました。
また、自分の原点を見つめるために、母のいる故郷の岐阜に帰りました。
実家に滞在中、地元北方町の図書館に行きました。こじんまりとしていますが灰色の瓦屋根で、とても趣があります。
◎ ◎
ちょうど郷土の偉人展が開催されていました。その一人、「日本の博物館の父」といわれている棚橋源太郎(1869~1961)という人の展示が目に留まりました。
説明書きによれば、棚橋さんは東京博物館の初代館長で、全国各地に博物館の建設を進めた人でした。また、全国の学校に理科室を造るように指導したのも棚橋さんだそうです。
理科室といえば、私も小学生の頃、いろんな実験をして、理科に対する興味が膨らんだものです。そして、理科室には、ホルマリン漬けの生き物がいたり、人間の骨格の模型があったりと不思議な世界が広がっていました。
メダカのような淡水生物を飼育して生きたまま見せる教育的な展示も棚橋さんが目指していたものだそうです。
また、子どもでも理解できるように、図解を使って説明をつけていたり、ガラスやセルロイド、セメントなどは完成品に至る過程を見せていくことを棚橋さんは大切にしていました。
もし棚橋さんがいなかったら、この国の理科教育も机上の教育になっていたかもしれないなぁと展示を見ながら思いました。
◎ ◎
棚橋さんは、私が生まれて間もなく亡くなりました。幼い頃、よく遊んでいた近所の子守神社の鳥居は棚橋さん兄弟が寄進したものだということも初めて知りました。
そうです。親も先生も話してくれなかったのです。
学校ではエジソンやナイチンゲールなど、遠くの偉人は教えてもらいましたが、郷土の偉人については教えてもらっていなかったのです。
私は大学で理科の教員免許を取りましたが、もし小学校の理科の授業中、先生が「君たち、日本中の理科室は棚橋さんが造ったんだ。そして棚橋さんはこの小学校の卒業生なんだ」と、こんな風に話してくれていたら、心がときめいて、もっと理科が好きになっていただろうなぁと思いました。
ちなみに、編集長の水谷は、15年ほど前、宮崎第一中学・高等学校の創立者である佐藤一一(さとう・かずいち)先生(故人)に依頼され、佐藤先生の書かれた『宮崎の偉人』(上)(中)(下)の原稿を編集し、鉱脈社から出版しました。これはもう宮崎県民の必読書ですね。
- 剣山の山頂を所有している人
- お米づくりから見えてきたこと
- 人生100年時代は生涯現役で
- 引き寄せられた出会いと尋ね人
- 人として美しく生きるって?
- 逆に励まされる電話掛け
- 「掃除をする」から「掃除に学ぶ」へ
- 入院中も楽しく友だちづくり
- 3か月前を思い起こす
- 何気ない一言で……
- その後、母はどうなったか……
- 30周年ありがとう講演会&祝賀会、宮崎会場
- おかげさまで30年
- 全国の中学校・高校に日本講演新聞を届けたい
- 終わりを思い描くことから始める
- 健康寿命、人生120年も夢じゃない
- 耳で聴く日本講演新聞、無料配信中
- 免疫力を上げるのは自助努力
- 英語を通して日本語を学ぶ
- 「馬の糞三つってありますか?」
- 取材する側から開催する側にも
- オンライン講演会の時代
- 書の持つエネルギー
- 子どもたちの健康を守りたい一心で
- 日本講演新聞のあるある
- 次の時代にも、そして次の世代にも…
- 購読料の値上げにご理解をお願いします
- 「日本」という枠にこだわらず
- 手つかずだから自然なのですね
- ステキな人生を作りましょう
2559号